
歴史上、日本の常に地球上で最も強力で高貴な戦士の一人でした。その中には武士道として知られる口承規範があり、忠誠と名誉が生存の基本原則であると述べられていました。この名誉意識は武士にとって生涯を通じて付きまとったものであり、やや暗い儀式にも結びついていました。
敗北に直面した場合、武士は切腹によって死ぬことを選択することができました。切腹とは、刃物で腹部を水平に切ることによって行われる儀式的自殺の一形態です。歴史家はこの不気味な行為がいつ始まったかは定かではありませんが、その起源はおそらく 12 世紀末頃であると考えられています。
名誉ある死
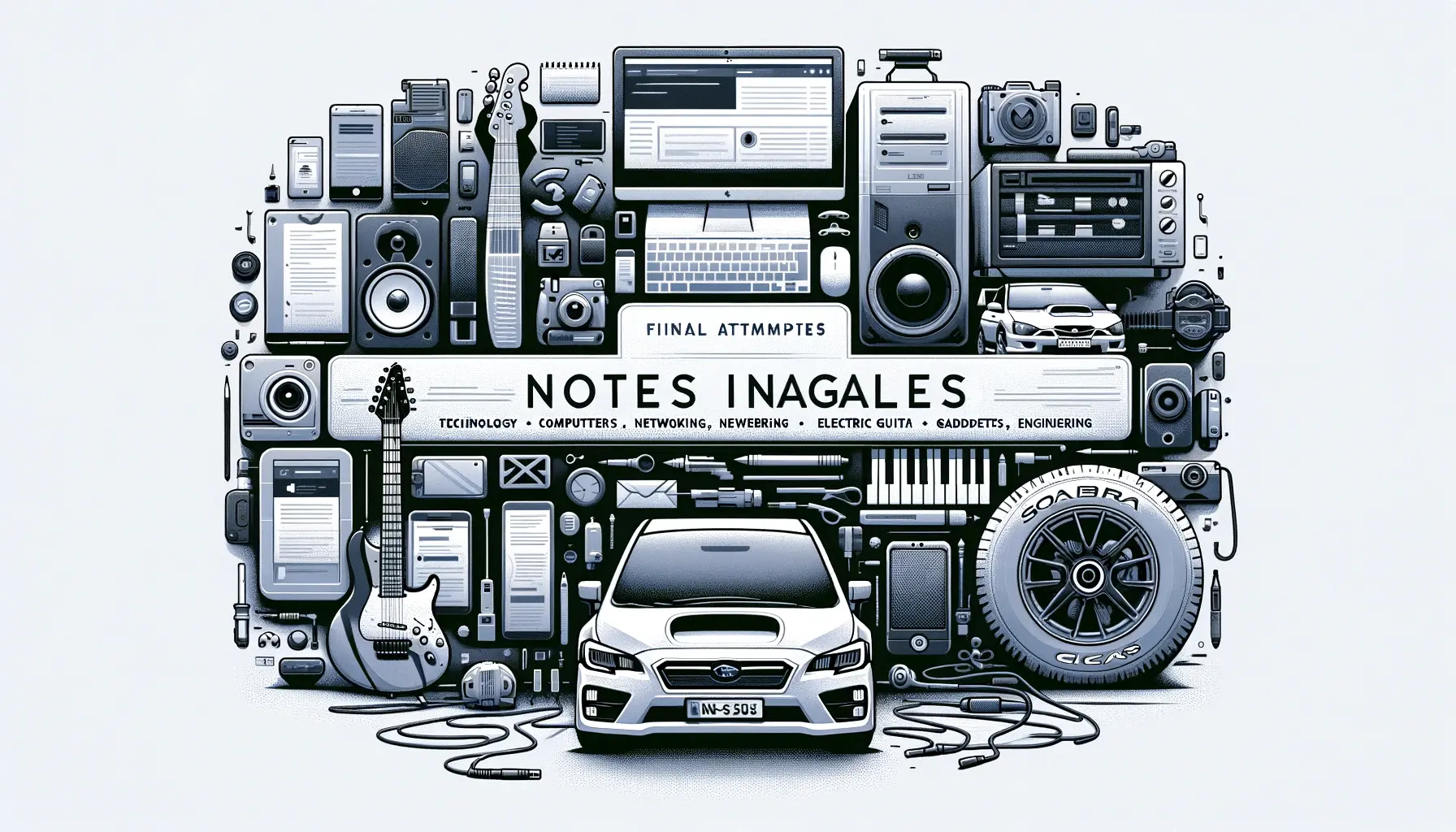
切腹は武士の規範と直接関係していますが、これらの武士から切腹が始まったわけではありません。東京大学教授の山本博文氏によると、切腹は平氏と源氏の間の内戦である源平合戦後の1189年に始まった可能性が高いという。

日本の伝統によれば、戦いで死ぬことは勇気ある行為でしたが、逃げることは卑怯な選択肢とみなされていました。武士は自ら命を絶つという、死という最後の苦渋の選択をすることになった。切腹は武士道の名誉規範の一部であり、この恐ろしい行為は中世を通してこのように見られ続けました。

しかし、この見方は時間の経過とともに、特に 15 世紀から 16 世紀にかけてほぼ継続的な内戦に悩まされた日本史の戦国時代 (1467 年から 1568 年) に変わりました。

切腹の変遷

戦国時代、大名たちは互いに、そして天皇に敵対し、それぞれが支配しようと競い合いました。こうして家臣たちは自ら権力を掌握しようと主君を裏切り始めた。これにより、切腹は戦士が死の際に名誉を保つための手段ではなくなり、軍事指導者が軍務を提供してくれた武士の命を救うための手段とみなされるようになった。

この最も有名な例の 1 つは、1582 年 6 月に羽柴秀吉の軍隊が清水宗治の城を包囲したときに起こりました。宗春は敗北が目前に迫っていることを悟り、敵対者たちと自決を取り決め、仲間全員の命をなんとか救った。
1871 年、日本では正式に終わりを迎え、それとともに武士の統治も終わりました。これによって武士道が日本社会から完全に消え去ったわけではなく、現代でも切腹例が数件ありました。しかし、状況はもはや同じではありませんでした。いずれにせよ、この行為は地域に根付いた文化的理念を体現したものであると言えるだろう。
ソース
